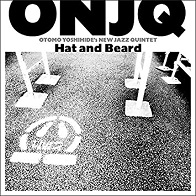
これ、これ、これ。これが聴きたかったんですよ。
‘Hat&Beard’ と‘Straight Up and Down’ の
大友良英・プレイズ・『アウト・トゥ・ランチ』に、思わず快哉を叫んじゃいました。
ぼくが大友良英のジャズに期待するパフォーマンスが、この2曲で繰り広げられています。
あらかじめ告白しておくと、
エリック・ドルフィーの『アウト・トゥ・ランチ』は、ぼくが偏愛するジャズの聖典。
その昔、このアルバムにジャズのひとつの理想郷を見つけてから、
このアルバムをクサすジャズ評論家のテキストは、読む価値無しとみなしています。


大友良英は、民俗音楽研究の江波戸昭教授の同じゼミ生というよしみもあって、
ノイズ/音響に関心はないものの、気になる音楽家としてずっと意識をしていました。
じっさい、大友が手がけた香港映画のサウンドトラック『女人、四十』(95)や、
グラウンド・ゼロの『革命京劇』(95)は、愛聴していましたからね。
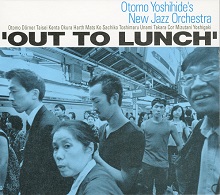
でも、本格的に大友に注目するようになったのは、
ONJQ(大友良英ニュー・ジャズ・クインテット)を結成して、
ドルフィーやオーネット、アイラーなどのジャズをやるようになってから。
クインテットからオーケストラへ発展したONJOが05年に発表した
『アウト・トゥ・ランチ』を丸ごとカヴァーした作品には、心底敬服したものです。
ドルフィーの音楽は唯一無比なあまりに、死後彼の音楽を継承する者は現れず、
コルトレーンやモンクのように楽理研究されることもなく、
メソッド化されないまま、放り出されていました。
そんなドルフィーに大友が真っ正面から向き合い、
ドルフィーの音楽を血肉化して演奏してみせたことは、
同世代の日本人として誇らしかったです。
ただ、正直言ってあの作品を愛聴したかと問われると、
ちょっと答えを言い淀んでしまうんですね。
Sachiko M、中村としはる、宇波拓といった音響派の音楽家たちは、
「エリック・ドルフィーのジャズ」にはジャマとしか思えませんでした。
もちろんこのアルバムは、大友がドルフィー以降のフリー、ノイズ、音響を経た地点から、
『アウト・トゥ・ランチ』をフィードバックしようという試みなのだから、
そこにジャズの影だけを追うことは間違いなことは、重々承知なんですけれど。
「ここのパート、退屈」とか「このインプロ、いらない」と思う場面があったのも、
正直な感想。
反対に、音響派のミュージシャンにとっても、
ドルフィーの『アウト・トゥ・ランチ』でなければならない理由はそこにはなく、
単なる素材として演奏しているようにしか聞こえなかったからです。
ジャズ・ミュージシャンには思い入れのある『アウト・トゥ・ランチ』も、
音響派のミュージシャンにとってはただの楽曲にすぎず、熱量がまるで違うみたいな。
で、今回はオーケストラでなく、クインテットに戻り、
メンバーを類家心平(tp)と今込治(tb)に代えて出した新作、
大友のジャズを期待するファンには、最高の仕上がりなんです。
クインテットの初期から演奏してきたオリジナル曲の‘Flutter’ はじめ、
これまでにさまざまなスタイルでカヴァーしてきた
オーネットの‘Lonely Woman’ もやっていて、大友のジャズ観が凝縮されています。
ノイズ、音響、インプロ、フリー・ジャズ、劇伴と多方面に渡る大友の音楽性のなかで、
音響を経たジャズの快楽を求めるファンには、絶好のアルバムですよ。
大友良英ニュー・ジャズ・クインテット 「HAT AND BEARD」 F.M.N. Sound Factory FMC051 (2020)
o.s.t. music by 大友良英 「女人,四十。」 Sound Factory STK003 (1995)
Ground-Zero 「革命京劇 -REVOLUTIONARY PEKINSE OPERA-」 Trigram TR-P909 (1995)
大友良英ニュー・ジャズ・オーケストラ 「OUT TO LUNCH」 ダウトミュージック DMF108 (2005)